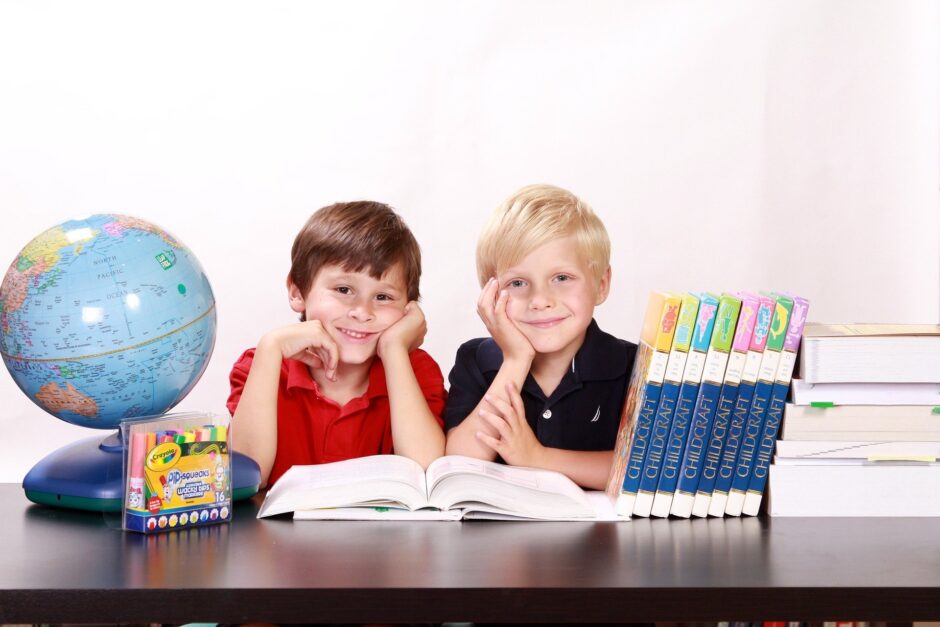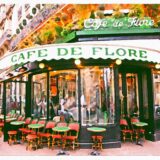本日も教育書になります。
『「うまくいかない」から考える』という本を読みました。この本は若手教師12人の失敗談をもとに今後の指導のしかたを考えるという内容です。
この本の著者である、片山さん、若松さんはコーチングやファシリテーションの本でお世話になっています。とても分かりやく、実践にも活かせる本なのでよろしければお読みください。
失敗談から考えるというのが大切だなと私は思います。最近は失敗したらもう終わりというような風潮があるのではないかと思っています。原稿を読み間違えたり、間違った事をしてしまったことに対する風当たりがかなり厳しくなっています。
このような環境だと、失敗することを極度に恐れてチャレンジしなくなったり、最悪失敗したことを隠してしまったりすることが起こると思います。
なので、まずは失敗してもいい環境をどんな組織であろうと創っていくことが必要です。心理的安全性です。それが、失敗から学ぶことができる第一歩だと考えています。
本書の中で私が人材育成をする上でポイントとなる3つのことを書いていきます。参考になれば幸いです。
1省察的経験について
世界的に影響を与えたアメリカの教育哲学者のジョン・デューイ(1975)は、「経験(experience)」に着目しました。彼は、単なる活動は慣例上経験と呼ぶに過ぎず、経験とはいえないと考えました。思考という要素を何ら含まない経験では、意味を持つ経験にはなりえない。経験を振り返り、そこに熟慮が見られることによって、経験の質が変わるというのです。そうした経験のことを、デューイは「省察的経験(reflective experience)」と表現しています。
『「うまくいかない」から考える』より
ただ経験するだけではだめだと。成長する、前に進んでいくためには経験したことを「思考」して振り返ることが大事だそうです。
思考をしないで経験を重ねるだけでもある程度の力は身につくのではないかと思います。しかし、より自分の力を引き出すには常に思考することが大切だと考えます。
例えば、学校では授業を創っていく際に学習指導要領や教科書の指導書などを活用します。まあ指導書通りに授業を行えば成長はできます、一応。
でも、その際にその授業に自分の思いを重ね、「これを身に着けさせたい」「これを引き出したい」という気持ちあがあるとより一層成長できると考えています。
さらに、それだけ思考する必要もあるので、振り返りの時間がより深いものになると考えています。できればそれを、一人だけではなく後輩含め様々なグループでできるとよいと思っています。
2「事実承認」を積み重ねる
事実承認とは、例えば、「さっきは、子どもたちが楽しそうにしていたね」「理科の準備、工夫しているね」「今日も体調よさそうだね」のように、ありのままを認めて承認することです。言われた方は、「自分のことをちゃんと見てくれている」と思いますし、職員室で日頃のコミュニケーションが増えるきっかけにもなります。
『「うまくいかない」から考える』より
これは、いろいろな組織で活用できることだと思います。「事実承認」とは違い、結果を褒めることは「結果承認」というようです。
ただ、この結果承認は、良い結果を出し続けていかないと、認めてもらえないという辛い状況に陥ることが考えられます。
なので、今頑張っている、努力している中でそれを認めることが「事実承認」です。これを子どもや職場仲間に続けられれば、良い関係性が築けるだろうと思いました。
また、相手が意識していない「自分の良さ」に気付く事ができるというメリットもあります。良いことづくめの「事実承認」ぜひ2学期から実践していきます。
3「PM理論」を活用する。
ところで、「全体を見る」とはどういうことでしょうか。学級に30人いれば、30人の個々の子どもを見ながら、それぞれがどの程度わかっているのかやどのように考えているのかなどを瞬時に理解し、同時に教室全体に漂う空気を察知して、そのうえで必要だと思われることを学級全体に即座に還元するということです。
『「うまくいかない」から考える』
PM理論についてはぜひ調べてみてください。個別に配慮が必要な子どもに対応するのも大切ですが、全体を見て引っ張っていくことも求められます。この2つの要素をバランス良く保っていくことが学級担任に必要とされる大切な力です。
この力を高めていくために大切なことは「メタ認知」であると考えます。なぜなら、子どもたちからどう見られているかを常に俯瞰することで指導のバランスを取ることができるからです。
「メタ認知」に関しては、以前に記事に書きましたのでよろしけれよろしければお読みください。
自分の行動・指導をビデオにとったり、同僚に観てもらったりすることも良いのではないかと思います。
以上が『「うまくいかない」から考える』から3つのポイントで人材育成を考えるになります。
最後までお読みいただきありがとうございました。